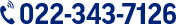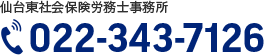うつ病だと障害年金はいくらもらえる?等級別の金額目安と受給の流れを社労士が解説
目次

あなたは、
「障害年金って具体的にいくらもらえるの?」
「自分はもらえるのかな?」
「障害年金ってなんだか難しそう…」
とお考えではありませんか?
障害年金は、病気やケガによって日常生活に支障がある方の生活を支え、治療に専念するための公的な支援制度です。もし、うつ病の症状で日常生活や仕事に制限がある場合、月に6万円から20万円ほどの年金を受け取れる可能性があります。年間では約60万~240万円を受け取れる計算です。
この記事では、うつ病による障害年金の受給額や申請の流れについて、社労士がわかりやすく解説します。
うつ病で障害年金はいくらもらえる?等級別の受給額
障害年金の受給額は、年間で約60万~240万円と幅があります。なぜなら以下の要因によって金額が決定されるためです。
・初診日の時点でどの年金制度に加入していたか
・うつ病の「程度」
うつ病の「程度」というのは、障害年金では「等級」として判断されます。
障害基礎年金(1級・2級)の受給額
障害基礎年金は、初診日の時点で国民年金に加入していた方が対象です。
障害基礎年金では、障害等級は1級と2級しかありません。障害等級に応じて、以下の固定額が支給されます。
■1級
1,039,625円(月額86,635円)
昭和31年4月1日以前生まれの方は1,036,625円(月額86,385円)
■2級
831,700円(月額69,308円)
昭和31年4月1日以前生まれの方は829,300円(月額69,108円)
さらに、いずれの等級においても子どもがいる場合は加算額があります。
■子どもの加算額
2人まで:1人につき239,300円(月額19,942円)
3人目以降:1人につき79,800円(月額6,650円)
子どもは18歳未満の高校卒業時(3月31日)まで、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子どもです。
※参考:日本年金機構|障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額
障害厚生年金(1級~3級)の受給額
障害厚生年金は、初診日の時点で厚生年金・共済年金に加入していた方が対象です。
障害厚生年金には等級が1~3級、そして障害手当金(一時金)があります。また、配偶者の加算額があるのも特徴です。
障害厚生年金の1~2級に該当する人は、障害基礎年金も同時に受け取れます。
具体的な計算としては、以下のとおりです。
■1級
障害基礎年金1級分 + (報酬比例の年金額) × 1.25 + 配偶者の加算額(239,300円)
■2級
障害基礎年金2級分 + (報酬比例の年金額) + 配偶者の加算額(239,300円)
■3級
(報酬比例の年金額)のみで、最低保証額が623,800 円です。
昭和31年4月1日以前生まれの方は622,000円
報酬比例の部分は、在職中の平均月収(賞与を含む)と厚生年金の加入期間をもとに計算されます。また、配偶者加算は「生計を維持している65歳未満の配偶者がいる場合」に適用されます。
※参考:日本年金機構|障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額
働きながらでも障害年金は受け取れる?
「働いているから障害年金はもらえない」と思い込んでいる方もいますが、誤解です。
うつ病の症状で就労に制限があれば、働きながらでも障害年金を受給できる場合があります。大切なのは「働けているかどうか」ではなく、「うつ病の症状により、どの程度生活や就労に制限があるか」です。
例えば、週に数日しか働けない、短時間勤務しかできない、職場で配慮を受けながら働いている、といった状況であれば、障害年金の対象となる可能性があります。
うつ病で障害年金を申請する流れ
障害年金の申請は、以下のような流れで進めます。
初診日の確認
うつ病で初めて病院を受診した日を「初診日」といいます。この日がいつなのか、どの病院だったのかを確認します。初診日により加入していた年金制度が決まるため、初診日の確認はとても重要です。
受診状況等証明書の取得
初診の病院で「受診状況等証明書」を取得します。初診の病院と現在通院している病院が同じ場合は不要です。
診断書の作成依頼
現在通院している病院で、障害年金用の診断書を作成してもらいます。日常生活の状況や症状について、ありのままに詳しく記載してもらうことが重要です。
病歴・就労状況等申立書の作成
ご本人やご家族が記載する書類です。うつ病の発症から現在までの経過や、日常生活での困りごとを詳しく記載します。
年金事務所への提出
必要書類をすべて揃えて、年金事務所に提出します。
障害年金のメリット・デメリット
事前に障害年金のメリット・デメリットを把握しておきましょう。
【メリット】
・生活費の心配が減る
年金という形で安定した収入があることで、経済的な不安が軽減され、治療に専念しやすくなります。
・精神的な安心につながる
経済的な不安による症状悪化を防ぐことにもつながります。
・障害年金には税金がかからない
障害年金は非課税のため、通知された金額がそのまま受け取れます。
・遡及して受給できる場合がある
障害認定日から申請日まで期間が空いている場合、最大5年分まで遡って一括で受け取ることができます。
・使い道に制限がない
生活保護の受給とは異なり、使用用途に一切制限がありません。
【デメリット】
・手続きが複雑
提出する書類が多く、年金制度の知識も必要なため、自分で進めるには労力がかかります。
・審査に時間がかかる
申請してから実際に受給できるまで、数カ月かかる場合があります。
・他の制度との調整がある
生活保護や傷病手当金を受給している場合は調整されます。また、障害年金の受給により、社会保険の扶養から外れる可能性もあります(年収180万円以上の場合)。
・定期的な現況報告が必要な場合がある
症状によっては1~5年ごとに診断書の提出が求められ、等級の見直しがおこなわれることがあります。
うつ病での障害年金申請は社労士に相談しましょう
うつ病による障害年金は、月額5万~20万円(年間60万~240万円)を受給でき、生活の大きな支えとなります。働きながらでも条件を満たせば受給可能です。
ただし、申請には専門的な知識と複数の書類が必要で、手続きが複雑です。「難しくてわからない」と感じたら、障害年金を専門とする社労士に相談しましょう。
一人で抱え込まず、適切なサポートを受けながら、あなたらしい生活を取り戻すための第一歩を踏み出していただければと思います。
障害年金の申請についてご不明な点などがございましたら、どんな些細なことでも構いませんので遠慮なくご連絡をいただければと思います。
メール、LINE、お電話(土日も対応)、いずれの方法でも結構ですのでお問い合わせをお待ちしております。
執筆者紹介

最新の投稿
- 1月 30, 2026コラム大人が片付けられないのは障害が原因?障害年金の受給条件と申請方法を社労士が解説
- 1月 30, 2026コラム仕事が覚えられないのは病気?ADHD等の診断を受けて障害年金を検討する方法を社労士が解説
- 1月 16, 2026コラム統合失調症の「親亡き後」はどうなる?お金の不安を軽減するための準備
- 1月 16, 2026コラム「お風呂がめんどくさい」はうつ病のサイン?働けなくなる前に知っておきたい収入面の対策






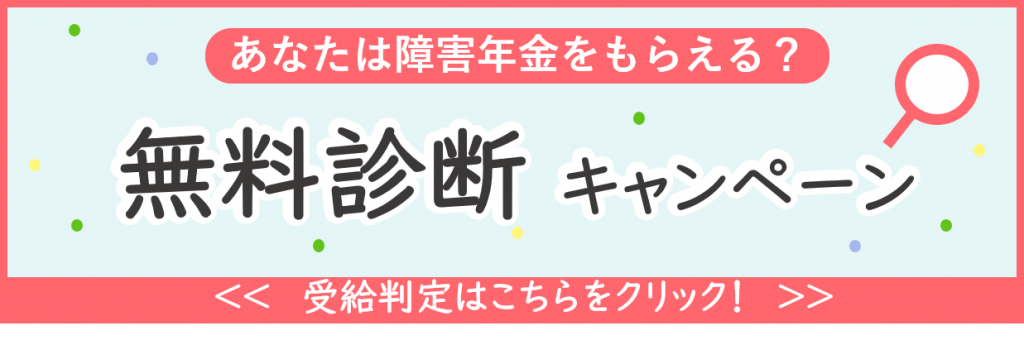
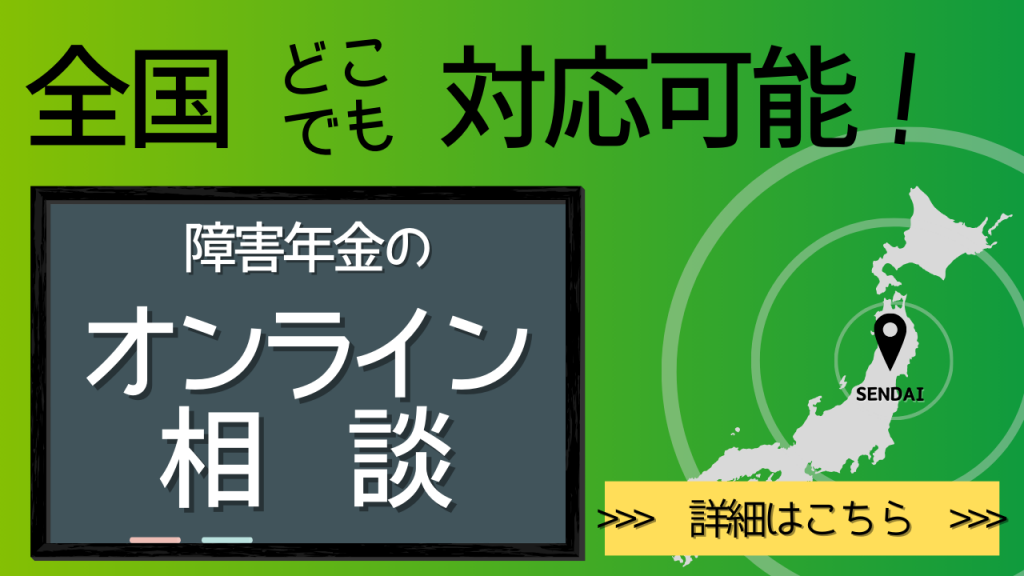
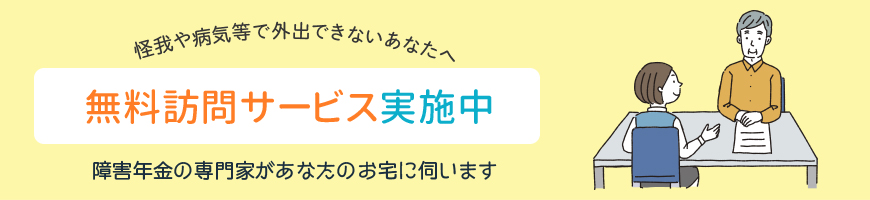
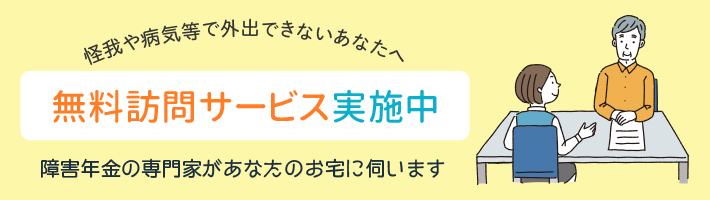


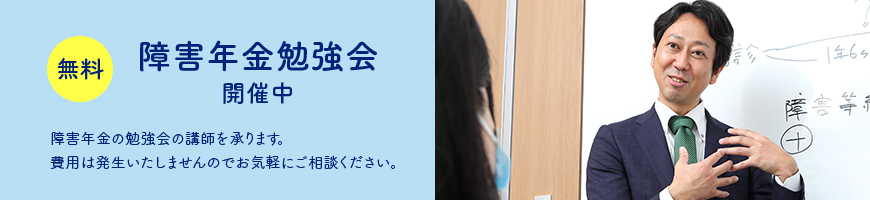
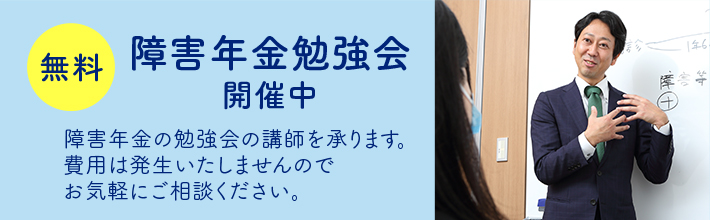
 キーワード検索
キーワード検索

 初めての方へ
初めての方へ